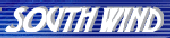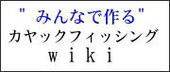2012年08月17日
足漕ぎカヤックでの再乗艇
先日の足漕ぎデビュー後に・・・やってみました、ホビーでの再乗艇
というのも、過去何度もやってた訓練が特殊な足漕ぎカヤックでも何なく通用するのか?
というのと、艤装してる状態だと難易度がどの程度上がるのか?
を体感してみたかったのと、ホビーの浸水具合のチェックを兼ねて・・・なインプレです。
▼使用したカヤックはたむぞうさんの新艇でもあるホビー・レボリューション13。

普段のフル艤装状態から、クーラー・竿・魚探モニターを外した状態。 詳細ですが・・・
・足漕ぎなので当然のミラージュドライブ+ホビー純正パドル&シート
・バウ側に魚探用マウント+魚探の台座
・スターン側のロッドホルダー部にホビー純正ロッドホルダー+3連ロッドホルダー
・スターン側のロッドホルダー部にランディングネット
・コックピットのサイドポケットにプライヤー&フィッシュグリップ
・ラゲッジには5フックのストリンガー
・ラゲッジのスカッパーホールに挿したフラッグシステム
になりますが、魚探に関する艤装以外は全てカヤック本体にリーシュで繋いであります。
▼まずはコチラの動画をご覧下さい。
たむぞうさんの練習シーンですが、裏がえったカヤックを持ち上げる様にひっくり返すのは難しかったらしく、普段ライドや130tで行っている方法では問題なくカヤックを復旧しています。
▼スタンディングも余裕だった安定性。

勝手が違う艇なので最初は考えながらでしたが、再乗艇の要領は同じなので問題ナシ。
▼ではでは、フルセットをお借りして・・・のっちも挑戦!
レボ13はフラット底でスカッパーホールも少ないので・・・ドコを掴もうかとイメージ。
今までの経験ではカヤックに乗り上がる(カヤックを体の下に引き込む)のが基本だったんですが、たむぞうさんの練習風景を見てて違う方法も試してみたくなりました。
▼まずは立ち上がって安定度を確認し・・・ドボン
その方法とは・・・
カヤックを復旧する時にハルに這い上がって反対側のトグルとかを掴むのではなく、自分側のトグルを真下に押す(鉄棒に乗る時みたいに真上に飛び上がるイメージで自分側のトグルに全体重を加重する)事で、反対側を浮かせて自分側に反対側のトグルを近づけよう・・・と。
動画では判断しにくいですが・・・
この方法だとバタ足で勢いをつけてカヤックに乗り上げる必要もなく、うつ伏せでハルに寝そべる(カヤックを水面に押さえつけてる)時間も短縮できるのでスピーディーでした。
カヤックを裏返す時には最初に反対側を持ち上げるのが重くて大変なので、その大変な部分を加重のかけ方と加重をかけるポイントにより軽減する事ができる気がしました。
と、特殊な足漕ぎカヤックでも難なく再乗艇が可能で新たな発見もあった訳ですが・・・
▼着岸してリアハッチを開けてみると・・・水がタップタプです

▼リアハッチからラダー側を覗いた写真がコレだ!
カヤックは3回転しかしてないのに・・・写真下側の色の違う部分は全て浸水した海水
(たむぞうさんは這い上がり加重方式で2回転、のっちはノー加重方式で1回転)
砂浜が傾斜してるので水はスターン側に寄ってましたが、それでもこんな感じでシート下付近まで水が溜まってました。 ゴムハッチを搭載してるライドでは何回転しても数滴程度しか浸水しなかったので、ビルジポンプは必須アイテムですね!
▼ドレンからの排水ではしばらくジョロジョロと・・・何リットルなのかは見当もつきません

でもでも、練習中は知らなかったとはいえこんなに浸水してた状態でも余裕でスタンディングできてた訳ですから、安定性が優れてるのは間違いなさそうです。
とはいっても、浸水しないに越した事はないので・・・色々と意見を聞いたり考えてもみたり。
▼コレが原因なんじゃないか・・・と推測しています。

陸上でカヤックを裏返した状態で同じ様に加圧してみるとわかるんですが・・・
丸みを帯びたレボ13はハルに加重が加わると形状が潰れる感じになります。
(カヤックを裏返す為にハルに這いつくばってる時点で体重により加圧されてる訳ですね。)
で、体重により加圧されてたカヤックをひっくり返す時には当然加重が抜けます・・・
と同時にカヤックは元の形へと戻ろうとしますので、加圧によりカヤック内部の空気がドコかの隙間(レボの場合は多分フロントハッチ)からカヤック外へと押し出され、元の形に戻る時にポンプ式で海水を吸い込んでしまうのでは?
と考えられたので、次回はノー加重方式のみ・・・の後に浸水具合をチェックしてみよう。。。

というのも、過去何度もやってた訓練が特殊な足漕ぎカヤックでも何なく通用するのか?
というのと、艤装してる状態だと難易度がどの程度上がるのか?
を体感してみたかったのと、ホビーの浸水具合のチェックを兼ねて・・・なインプレです。
▼使用したカヤックはたむぞうさんの新艇でもあるホビー・レボリューション13。

普段のフル艤装状態から、クーラー・竿・魚探モニターを外した状態。 詳細ですが・・・
・足漕ぎなので当然のミラージュドライブ+ホビー純正パドル&シート
・バウ側に魚探用マウント+魚探の台座
・スターン側のロッドホルダー部にホビー純正ロッドホルダー+3連ロッドホルダー
・スターン側のロッドホルダー部にランディングネット
・コックピットのサイドポケットにプライヤー&フィッシュグリップ
・ラゲッジには5フックのストリンガー
・ラゲッジのスカッパーホールに挿したフラッグシステム
になりますが、魚探に関する艤装以外は全てカヤック本体にリーシュで繋いであります。
▼まずはコチラの動画をご覧下さい。
たむぞうさんの練習シーンですが、裏がえったカヤックを持ち上げる様にひっくり返すのは難しかったらしく、普段ライドや130tで行っている方法では問題なくカヤックを復旧しています。
▼スタンディングも余裕だった安定性。

勝手が違う艇なので最初は考えながらでしたが、再乗艇の要領は同じなので問題ナシ。
▼ではでは、フルセットをお借りして・・・のっちも挑戦!

レボ13はフラット底でスカッパーホールも少ないので・・・ドコを掴もうかとイメージ。
今までの経験ではカヤックに乗り上がる(カヤックを体の下に引き込む)のが基本だったんですが、たむぞうさんの練習風景を見てて違う方法も試してみたくなりました。
▼まずは立ち上がって安定度を確認し・・・ドボン

その方法とは・・・
カヤックを復旧する時にハルに這い上がって反対側のトグルとかを掴むのではなく、自分側のトグルを真下に押す(鉄棒に乗る時みたいに真上に飛び上がるイメージで自分側のトグルに全体重を加重する)事で、反対側を浮かせて自分側に反対側のトグルを近づけよう・・・と。
動画では判断しにくいですが・・・
この方法だとバタ足で勢いをつけてカヤックに乗り上げる必要もなく、うつ伏せでハルに寝そべる(カヤックを水面に押さえつけてる)時間も短縮できるのでスピーディーでした。
カヤックを裏返す時には最初に反対側を持ち上げるのが重くて大変なので、その大変な部分を加重のかけ方と加重をかけるポイントにより軽減する事ができる気がしました。
と、特殊な足漕ぎカヤックでも難なく再乗艇が可能で新たな発見もあった訳ですが・・・
▼着岸してリアハッチを開けてみると・・・水がタップタプです


▼リアハッチからラダー側を覗いた写真がコレだ!

カヤックは3回転しかしてないのに・・・写真下側の色の違う部分は全て浸水した海水

(たむぞうさんは這い上がり加重方式で2回転、のっちはノー加重方式で1回転)
砂浜が傾斜してるので水はスターン側に寄ってましたが、それでもこんな感じでシート下付近まで水が溜まってました。 ゴムハッチを搭載してるライドでは何回転しても数滴程度しか浸水しなかったので、ビルジポンプは必須アイテムですね!
▼ドレンからの排水ではしばらくジョロジョロと・・・何リットルなのかは見当もつきません


でもでも、練習中は知らなかったとはいえこんなに浸水してた状態でも余裕でスタンディングできてた訳ですから、安定性が優れてるのは間違いなさそうです。
とはいっても、浸水しないに越した事はないので・・・色々と意見を聞いたり考えてもみたり。
▼コレが原因なんじゃないか・・・と推測しています。

陸上でカヤックを裏返した状態で同じ様に加圧してみるとわかるんですが・・・
丸みを帯びたレボ13はハルに加重が加わると形状が潰れる感じになります。
(カヤックを裏返す為にハルに這いつくばってる時点で体重により加圧されてる訳ですね。)
で、体重により加圧されてたカヤックをひっくり返す時には当然加重が抜けます・・・
と同時にカヤックは元の形へと戻ろうとしますので、加圧によりカヤック内部の空気がドコかの隙間(レボの場合は多分フロントハッチ)からカヤック外へと押し出され、元の形に戻る時にポンプ式で海水を吸い込んでしまうのでは?
と考えられたので、次回はノー加重方式のみ・・・の後に浸水具合をチェックしてみよう。。。
2012年06月12日
リーシュするならナイフは必須!
カヤックフィッシングをするにあたって、色々な道具を積み込んでる事かと思いますが・・・
特に水没させたくない物にはリーシュ(カヤックや体と道具類を繋ぐロープの類)してる事でしょう。 ロッド・ネット・ランディングツール・プライヤー・・・などなど多数
他にものっち的に大切だと思ってるのがカヤックと自分を繋ぐリーシュ、唯一の動力源となるパドルへのシーシュ。 (←この2点は色々な意見があるので・・・個人的にはです。)
要するに、カヤックのコックピット上では複数のリーシュが散乱してる訳です
リーシュの長さや素材の種類も用途によって様々なんですが・・・
のっちの場合はナイフで切断可能なモノを選んでリーシュ用に使っています。
理由はただ1つ。
カヤックから沈(転覆)して再乗艇(カヤックをひっくり返して這い上がる)する時に、各リーシュが体に巻きついてしまい身動きが妨げられてしまう事があります。
そんな緊急事態な時の為に肌身離さずナイフを常備してる訳ですが、そのナイフで切断可能なリーシュでなければならないのは言うまでもありませんね!
(参考までに、再乗艇とはアンな感じやコンな感じで行います。凪な海峡での練習風景なので、実際に沈するシチュエーションでは更に難易度は高まる事でしょう。)
と、前置きが長くなってしまいましたが・・・
以前、「Go! Kayaking」のけーふぁく隊長さんが紹介されていたナイフの記事見て以来、のっちもマネて使っていますので、今回はコイツについて紹介します。
▼GILL パーソナルレスキューナイフ MT002

2011に登場した折り畳み式マリンナイフで、不意に閉じない様セーフティロック機構付き。
ブレード部分はマリングレード420のステンレス素材にチタンコーティングを施してあり、錆に非常に強く出来ています。 (ベルトループ付き収納ポーチが付属してるので便利。)
▼ハンドル部分にはGillのロゴが刻まれ、グリップ感を向上。

折り畳み時の寸法120mm 広げた時の寸法200mm ブレードの寸法85mm
▼裏側にはPFDなどに装着可能なハーネスクリップ付きです。

▼ハンドル部にはウェビングカッターも内蔵。

▼素早く効果的にロープを切れる様に、のこぎり状にデザインされたブレード部。

先端は丸く加工されていて刃にはなっていないので・・・
狭い隙間にツッ込みたい場合でも誤ってケガをする心配も少ないかと思われます
▼で、こんな感じにリーシュ類をしっかりホールドしてくれるする訳です。

(切れ味についてはコチラの記事を参照してみて下さい。)
レスキュー用なので用途が限られてしまうし、何でも切れるという訳ではありませんが・・・
通常使われてる様なリーシュであればスパッとなので、デザイン的にも気に入っています。
ド定番でもあるPEラインは細くても素手では切れませんし、リーシュの類が邪魔してカヤックに再乗艇できなくなる様ではシャレになりませんからね
これからの時期はカヤックデビューする方が多くなる季節ですし、台風等でウネリも増えたりするので、自分の身を守れる装備は必須かと思います。。。
特に水没させたくない物にはリーシュ(カヤックや体と道具類を繋ぐロープの類)してる事でしょう。 ロッド・ネット・ランディングツール・プライヤー・・・などなど多数

他にものっち的に大切だと思ってるのがカヤックと自分を繋ぐリーシュ、唯一の動力源となるパドルへのシーシュ。 (←この2点は色々な意見があるので・・・個人的にはです。)
要するに、カヤックのコックピット上では複数のリーシュが散乱してる訳です

リーシュの長さや素材の種類も用途によって様々なんですが・・・
のっちの場合はナイフで切断可能なモノを選んでリーシュ用に使っています。
理由はただ1つ。
カヤックから沈(転覆)して再乗艇(カヤックをひっくり返して這い上がる)する時に、各リーシュが体に巻きついてしまい身動きが妨げられてしまう事があります。
そんな緊急事態な時の為に肌身離さずナイフを常備してる訳ですが、そのナイフで切断可能なリーシュでなければならないのは言うまでもありませんね!
(参考までに、再乗艇とはアンな感じやコンな感じで行います。凪な海峡での練習風景なので、実際に沈するシチュエーションでは更に難易度は高まる事でしょう。)
と、前置きが長くなってしまいましたが・・・
以前、「Go! Kayaking」のけーふぁく隊長さんが紹介されていたナイフの記事見て以来、のっちもマネて使っていますので、今回はコイツについて紹介します。
▼GILL パーソナルレスキューナイフ MT002

2011に登場した折り畳み式マリンナイフで、不意に閉じない様セーフティロック機構付き。
ブレード部分はマリングレード420のステンレス素材にチタンコーティングを施してあり、錆に非常に強く出来ています。 (ベルトループ付き収納ポーチが付属してるので便利。)
▼ハンドル部分にはGillのロゴが刻まれ、グリップ感を向上。

折り畳み時の寸法120mm 広げた時の寸法200mm ブレードの寸法85mm
▼裏側にはPFDなどに装着可能なハーネスクリップ付きです。

▼ハンドル部にはウェビングカッターも内蔵。

▼素早く効果的にロープを切れる様に、のこぎり状にデザインされたブレード部。

先端は丸く加工されていて刃にはなっていないので・・・
狭い隙間にツッ込みたい場合でも誤ってケガをする心配も少ないかと思われます

▼で、こんな感じにリーシュ類をしっかりホールドしてくれるする訳です。

(切れ味についてはコチラの記事を参照してみて下さい。)
レスキュー用なので用途が限られてしまうし、何でも切れるという訳ではありませんが・・・
通常使われてる様なリーシュであればスパッとなので、デザイン的にも気に入っています。
ド定番でもあるPEラインは細くても素手では切れませんし、リーシュの類が邪魔してカヤックに再乗艇できなくなる様ではシャレになりませんからね

これからの時期はカヤックデビューする方が多くなる季節ですし、台風等でウネリも増えたりするので、自分の身を守れる装備は必須かと思います。。。
タグ :レスキューナイフ
2012年01月22日
真冬の再乗艇訓練 「チームSJT」
荒れた天候や怪しい予報の時には漕ぎ出さない事が大前提なカヤックフィッシング。
しかし、たとえ凪であっても一瞬の油断でバランスを崩せば沈する事もあるだろうし・・・
急な天候変化によるウネリや地形的な白波などでヒヤッとした場面も多々あったし・・・
いくら釣りに特化したフィッシングカヤックだとしても沈する可能性はいくらでもある訳です。
そんな万が一の事態に備えて再乗艇の練習は必須科目なのがカヤックフィッシング。
とはいえ、未だ夏の暖かい海での軽装でしか練習した事がなかったのっち
前々から冬の装備や様々なシチュエーションを想定して練習しとかなきゃと思ってたんですが、つい釣りに夢中でズルズルと後回しになってて・・・でようやく練習してみました。
12月上旬の話・・・
▼FUNさんの呼びかけにより集った有志、その名も「チームSJT」のメンバー。(他にも大勢)

メンバーは再乗艇の練習をそれぞれこなしてはいますが・・・
今回は様々な状況を意図的に作り出し、危険予知と疑似体験による再乗艇訓練です。
▼当日のコンディション。
普段なら風待ちする様なコンディションから、少しづつ収まり傾向にあった向かい風。
それでも沖には白波が立っていて、ある程度波っ気のある状況でした。
のっちは初めての冬訓練という事もありフル艤装ではありませんでしたが、中には艤装や色々な小物類をリーシュしたりして挑戦するメンバーも・・・でした。
訓練といっても危険な訳ですから、事前の打ち合わせを念入りにし、もしもの時にはスグに救助できるようにメンバーはポジショニングしつつ・・・各々スキルupを目指します。
▼まず、先陣を切ったのはチームで唯一の女性KFA、特攻隊長なkarikaiさん。

また、唯一のホビー艇オーナーでもあり、裏返ったカヤックから飛び出すミラージュドライブをモノともせずにカヤックをひっくり返してサクッと乗り込んでました。
で、慣れてない「艤装してる側」からも挑戦しますが難易度は高くなるらしく・・・
反対側まで泳いで艇をグルッと回り込んでみたり、ミラージュドライブを挿す穴を利用すればカヤックを楽に裏返せる発見もあったようです。
無駄がなく見事な再乗艇っぷりを目の当たりにした男性メンバー達
負けてられるか・・・と、競い合う様に次から次へとダイブしまくりとなりました。 (笑)
▼コロニャーさんはシートについて思案してました。

不安定な状態のカヤックに乗り込んだ際に、ハイバックで自立しているシートについて以前から色々と考えてた事があったようです。
うつ伏せに乗り込んだ姿勢から着座姿勢に移る際に、シートの背もたれがなければ・・・と。
そこで、簡単に折れ曲がってくれる構造や、柔らかい素材ならば・・・と、イメージを膨らませてたようです。
また、何度も繰り返していると体力が奪われてしまう危険があるので、少ない回数で確実に再乗艇する為の方法を考えていました。
▼パドリングジャケット&パンツで挑んだうにおさん。

沖から陸に向けて強めの風が吹いていた事もあり、乗り込もうとした際に傾いたカヤックが風をモロに受けてしまい失敗してしまいました。
▼その模様の動画ですが・・・逆光だしアラいのはご了承下さい
何度も繰り返しているうちにリーシュ類が足に絡まったりして更に困難な状況になりますが、落ち着いてソレらを解くと無事に乗り込む事に成功です。 が・・・
何度もカヤックとPFDが擦れ合ってた為に、再乗艇後にはメインチャックが全開。 (怖っ)
万が一の対策として、PFDのジッパーが不意に開かぬように「閉めた後に開け止めのループに固定する」という予防策を提案されてました。
また、パドリングジャケット&パンツでは1度の落水ではほとんど濡れなかったそうですが、この後ガンガン練習してたらジワジワと浸水してまったようです。
▼sirosixさんもパドリングジャケット&パンツで挑んでました。

何なく何度も再乗艇を繰り返してましたが・・・
やはり、ウエアの上下の隙間からジワジワと染み込んでしまったそうです。
といってもビショビショになる訳ではないので、少ない回数で確実に再乗艇できる技術と、インナーを工夫して正しく着用すれば・・・アリな様ですね。
(sirosixさんから「パドリングジャケット&パンツ」での詳しいインプレのコメント頂いていますので、この記事のコメント欄にて確認してみて下さい・汗)
▼banzyさんはドライスーツでのチャレンジの末、新たな課題を発見されてました。

ドライスーツでは空気の逃げ場がないので、落水した際の水圧で空気が上半身に集中してしまい身動きの妨げになってしまうようです。
試しにのっちは水中で首のラテックスからエア抜きしてみましたが・・・
両脇を絞めながら腕部に空気が溜まらないようにしつつ、波が低いタイミングでなら首からでもバフッと抜けてくれました。
漕ぎ出す前にしっかりエア抜きしたつもりでも・・・まだまだだったようです
▼のっち&たむぞうさんはタンデム艇でトライ!

横波を受けた事を想定して・・・陸側に落水。
お互いにリーシュ類の絡まり具合を確認したうえで、ソレを解くのかカヤックを裏返すのか・・・と順序を決めます。
▼で、まずはリアシートへたむぞうさんが乗り込みバランスを保持し・・・

次にフロントシートへのっちが再乗艇するというパターンがベストと感じられました。
この時にたむぞうさんが波側に重心移動しながら艇をフラットにコントロールしてくれてたので、沖からの風や波を受けながらでも楽々と乗り込む事ができました。
あと、のっち的な乗り込みスタイルですが・・・バタ足ってほとんどしてません。
垂直に浮いてる状態でしっかりとカヤックのどこかを両手を伸ばした状態で掴み、次に足を後方に持ち上げながら体を水面と並行になるようにコントロールします。
この時、足を広げた方がバランスがとれて安定します。
で、片足ごとに左右交互で1発ずつ強いキックを打ち込み、下半身が水面方向へ浮き上がった感覚の時に瞬間的にカヤックを腹の下に引き込む感じです。
イメージとしては留まってるカヤックに体を乗り上げるのではなく、水面に跳ね上がった際にできた体との隙間にカヤックを滑り込ませる感じです。
▼ホエールさんはパドルフロートを使って試行錯誤してました。

初めて使うアイテムながらも、どの様にして使うのがベストなのか・・・を試していました。
カヤックに乗り込む前にパドルを艇上に押さえつけ、フロートに足を掛けて乗り込んでた様な・・・ただ、このアイテムはいつでも取り出せるポジションに収納しとかなければ使う事すらできません。 使いこなせる様になるには練習あるのみですが、お助け便利グッズとして常備しとくのもアリですね。
▼お次は、浸水してしまったカヤックをズリ上げて排水する術を考えてみます。

まずは浸水してしまったカヤックをズリズリとコックピットへ・・・
▼で、こんな風に(ハッチを開けたつもり)豪快に排水。

シットインなどではこういったレスキュー訓練が常らしく、シットオンでも浸水具合によってはバウを持ち上げてドレンから抜く事もパワー系な人なら・・・できそうかな?
ただし、かなり訓練しないと困難なのは容易に想像できるので無理は禁物ですね。
続いては・・・
▼さらに難易度を上げるべくドレンを全開状態、そのままハッチからも水を入れてみました。

カヤック内にある程度浸水すると艇の挙動が不安定になり、そのまま漕ぐにも足を広げてバランスを取りながらの手漕ぎじゃないと・・・しかもスピードが出ません。
この状態での再乗艇に関しても、カヤックを裏返すのが難しいだけでなく、乗り込んでもフラつくので再乗艇に慣れたFUNさんでも再沈したりしてしまいます。
ここまでやってみると、今度は一体どれくらいまでの浸水ならば再乗艇できるのか?
という疑問も出てくる訳で…FUNさんが体をはって検証してみる事に。
ドレンの閉め忘れの末に何かしらの衝撃でハッチが吹っ飛び、浸水してしまったカヤックから落水してしまい再乗艇にも失敗・・・という、まさにピンチな状況を想定しました。
▼カヤックを裏返すつもりが、ハッチからガンガン浸水してしまい最終的には・・・
再乗艇する事も、カヤックを引き上げて排水する事もできません。
こうなってしまう前に118コールするべきなんでしょうが・・・実際には「自力で何とかしよう」と考えてしまう事でしょう。
なので・・・周囲に救助可能なアングラーが浮いてた事を想定して、こんな状況でも救助可能なのかどうかを検証してみます。
▼沈没してしまったカヤックをロープで牽引してみます。
パワフルな田吾作さんのマジ漕ぎ+追い風でも・・・かろうじて進む程度。
二次災害を防ぐ為にも沈むカヤックは潔く諦め、救助する側のアングラーが早急に118コールするのが正しい選択かと思われました。
で、落水してしまったアングラーの救助方法も考えてみました。
試してみたのは「カヤックのスターンにしがみついてもらい牽引する」という方法。
実際にFUNさんをうにおさんが牽引してみた感想として、「パラシュートアンカーを引き上げるのを忘れて漕いでた時」と同じくらいの漕ぎ感覚だったそうです。
漕ぎが強い方により、岸までの距離が近ければ可能なのかもしれませんが・・・
のっちの漕ぎでは無理せずカヤックにしがみついてもらいつつ118救助を待った方が良さそうです。
と、様々な訓練を終えた「チームSJT」。
まだまだスキル不足ではありますが、万が一の時に少しでも役立つ様にと前向きな練習。
今回得られた経験を踏まえつつ、今後も・・・少しずつだとしても己の安全マージンを上げてく練習を重ねて、末永く安全第一なカヤックフィッシングを楽しみたいです。。。
このような機会を設けてくれたFUNさんに感謝なのはモチロン、参加されたメンバーの試行錯誤が互いのスキルupに繋がる様に・・・またザブザブしましょうね~
真冬の海での再乗艇訓練、ホントにお疲れ様でした! m(_ _)m
しかし、たとえ凪であっても一瞬の油断でバランスを崩せば沈する事もあるだろうし・・・
急な天候変化によるウネリや地形的な白波などでヒヤッとした場面も多々あったし・・・
いくら釣りに特化したフィッシングカヤックだとしても沈する可能性はいくらでもある訳です。
そんな万が一の事態に備えて再乗艇の練習は必須科目なのがカヤックフィッシング。
とはいえ、未だ夏の暖かい海での軽装でしか練習した事がなかったのっち

前々から冬の装備や様々なシチュエーションを想定して練習しとかなきゃと思ってたんですが、つい釣りに夢中でズルズルと後回しになってて・・・でようやく練習してみました。
12月上旬の話・・・
▼FUNさんの呼びかけにより集った有志、その名も「チームSJT」のメンバー。(他にも大勢)

メンバーは再乗艇の練習をそれぞれこなしてはいますが・・・
今回は様々な状況を意図的に作り出し、危険予知と疑似体験による再乗艇訓練です。
▼当日のコンディション。
普段なら風待ちする様なコンディションから、少しづつ収まり傾向にあった向かい風。
それでも沖には白波が立っていて、ある程度波っ気のある状況でした。
のっちは初めての冬訓練という事もありフル艤装ではありませんでしたが、中には艤装や色々な小物類をリーシュしたりして挑戦するメンバーも・・・でした。
訓練といっても危険な訳ですから、事前の打ち合わせを念入りにし、もしもの時にはスグに救助できるようにメンバーはポジショニングしつつ・・・各々スキルupを目指します。
▼まず、先陣を切ったのはチームで唯一の女性KFA、特攻隊長なkarikaiさん。

また、唯一のホビー艇オーナーでもあり、裏返ったカヤックから飛び出すミラージュドライブをモノともせずにカヤックをひっくり返してサクッと乗り込んでました。
で、慣れてない「艤装してる側」からも挑戦しますが難易度は高くなるらしく・・・
反対側まで泳いで艇をグルッと回り込んでみたり、ミラージュドライブを挿す穴を利用すればカヤックを楽に裏返せる発見もあったようです。
無駄がなく見事な再乗艇っぷりを目の当たりにした男性メンバー達

負けてられるか・・・と、競い合う様に次から次へとダイブしまくりとなりました。 (笑)
▼コロニャーさんはシートについて思案してました。

不安定な状態のカヤックに乗り込んだ際に、ハイバックで自立しているシートについて以前から色々と考えてた事があったようです。
うつ伏せに乗り込んだ姿勢から着座姿勢に移る際に、シートの背もたれがなければ・・・と。
そこで、簡単に折れ曲がってくれる構造や、柔らかい素材ならば・・・と、イメージを膨らませてたようです。
また、何度も繰り返していると体力が奪われてしまう危険があるので、少ない回数で確実に再乗艇する為の方法を考えていました。
▼パドリングジャケット&パンツで挑んだうにおさん。

沖から陸に向けて強めの風が吹いていた事もあり、乗り込もうとした際に傾いたカヤックが風をモロに受けてしまい失敗してしまいました。
▼その模様の動画ですが・・・逆光だしアラいのはご了承下さい

何度も繰り返しているうちにリーシュ類が足に絡まったりして更に困難な状況になりますが、落ち着いてソレらを解くと無事に乗り込む事に成功です。 が・・・
何度もカヤックとPFDが擦れ合ってた為に、再乗艇後にはメインチャックが全開。 (怖っ)
万が一の対策として、PFDのジッパーが不意に開かぬように「閉めた後に開け止めのループに固定する」という予防策を提案されてました。
また、パドリングジャケット&パンツでは1度の落水ではほとんど濡れなかったそうですが、この後ガンガン練習してたらジワジワと浸水してまったようです。
▼sirosixさんもパドリングジャケット&パンツで挑んでました。

何なく何度も再乗艇を繰り返してましたが・・・
やはり、ウエアの上下の隙間からジワジワと染み込んでしまったそうです。
といってもビショビショになる訳ではないので、少ない回数で確実に再乗艇できる技術と、インナーを工夫して正しく着用すれば・・・アリな様ですね。
(sirosixさんから「パドリングジャケット&パンツ」での詳しいインプレのコメント頂いていますので、この記事のコメント欄にて確認してみて下さい・汗)
▼banzyさんはドライスーツでのチャレンジの末、新たな課題を発見されてました。

ドライスーツでは空気の逃げ場がないので、落水した際の水圧で空気が上半身に集中してしまい身動きの妨げになってしまうようです。
試しにのっちは水中で首のラテックスからエア抜きしてみましたが・・・
両脇を絞めながら腕部に空気が溜まらないようにしつつ、波が低いタイミングでなら首からでもバフッと抜けてくれました。
漕ぎ出す前にしっかりエア抜きしたつもりでも・・・まだまだだったようです

▼のっち&たむぞうさんはタンデム艇でトライ!

横波を受けた事を想定して・・・陸側に落水。
お互いにリーシュ類の絡まり具合を確認したうえで、ソレを解くのかカヤックを裏返すのか・・・と順序を決めます。
▼で、まずはリアシートへたむぞうさんが乗り込みバランスを保持し・・・

次にフロントシートへのっちが再乗艇するというパターンがベストと感じられました。
この時にたむぞうさんが波側に重心移動しながら艇をフラットにコントロールしてくれてたので、沖からの風や波を受けながらでも楽々と乗り込む事ができました。
あと、のっち的な乗り込みスタイルですが・・・バタ足ってほとんどしてません。
垂直に浮いてる状態でしっかりとカヤックのどこかを両手を伸ばした状態で掴み、次に足を後方に持ち上げながら体を水面と並行になるようにコントロールします。
この時、足を広げた方がバランスがとれて安定します。
で、片足ごとに左右交互で1発ずつ強いキックを打ち込み、下半身が水面方向へ浮き上がった感覚の時に瞬間的にカヤックを腹の下に引き込む感じです。
イメージとしては留まってるカヤックに体を乗り上げるのではなく、水面に跳ね上がった際にできた体との隙間にカヤックを滑り込ませる感じです。
▼ホエールさんはパドルフロートを使って試行錯誤してました。

初めて使うアイテムながらも、どの様にして使うのがベストなのか・・・を試していました。
カヤックに乗り込む前にパドルを艇上に押さえつけ、フロートに足を掛けて乗り込んでた様な・・・ただ、このアイテムはいつでも取り出せるポジションに収納しとかなければ使う事すらできません。 使いこなせる様になるには練習あるのみですが、お助け便利グッズとして常備しとくのもアリですね。
▼お次は、浸水してしまったカヤックをズリ上げて排水する術を考えてみます。

まずは浸水してしまったカヤックをズリズリとコックピットへ・・・
▼で、こんな風に(ハッチを開けたつもり)豪快に排水。

シットインなどではこういったレスキュー訓練が常らしく、シットオンでも浸水具合によってはバウを持ち上げてドレンから抜く事もパワー系な人なら・・・できそうかな?
ただし、かなり訓練しないと困難なのは容易に想像できるので無理は禁物ですね。
続いては・・・
▼さらに難易度を上げるべくドレンを全開状態、そのままハッチからも水を入れてみました。

カヤック内にある程度浸水すると艇の挙動が不安定になり、そのまま漕ぐにも足を広げてバランスを取りながらの手漕ぎじゃないと・・・しかもスピードが出ません。
この状態での再乗艇に関しても、カヤックを裏返すのが難しいだけでなく、乗り込んでもフラつくので再乗艇に慣れたFUNさんでも再沈したりしてしまいます。
ここまでやってみると、今度は一体どれくらいまでの浸水ならば再乗艇できるのか?
という疑問も出てくる訳で…FUNさんが体をはって検証してみる事に。
ドレンの閉め忘れの末に何かしらの衝撃でハッチが吹っ飛び、浸水してしまったカヤックから落水してしまい再乗艇にも失敗・・・という、まさにピンチな状況を想定しました。
▼カヤックを裏返すつもりが、ハッチからガンガン浸水してしまい最終的には・・・
再乗艇する事も、カヤックを引き上げて排水する事もできません。
こうなってしまう前に118コールするべきなんでしょうが・・・実際には「自力で何とかしよう」と考えてしまう事でしょう。
なので・・・周囲に救助可能なアングラーが浮いてた事を想定して、こんな状況でも救助可能なのかどうかを検証してみます。
▼沈没してしまったカヤックをロープで牽引してみます。
パワフルな田吾作さんのマジ漕ぎ+追い風でも・・・かろうじて進む程度。
二次災害を防ぐ為にも沈むカヤックは潔く諦め、救助する側のアングラーが早急に118コールするのが正しい選択かと思われました。
で、落水してしまったアングラーの救助方法も考えてみました。
試してみたのは「カヤックのスターンにしがみついてもらい牽引する」という方法。
実際にFUNさんをうにおさんが牽引してみた感想として、「パラシュートアンカーを引き上げるのを忘れて漕いでた時」と同じくらいの漕ぎ感覚だったそうです。
漕ぎが強い方により、岸までの距離が近ければ可能なのかもしれませんが・・・
のっちの漕ぎでは無理せずカヤックにしがみついてもらいつつ118救助を待った方が良さそうです。
と、様々な訓練を終えた「チームSJT」。
まだまだスキル不足ではありますが、万が一の時に少しでも役立つ様にと前向きな練習。
今回得られた経験を踏まえつつ、今後も・・・少しずつだとしても己の安全マージンを上げてく練習を重ねて、末永く安全第一なカヤックフィッシングを楽しみたいです。。。
このような機会を設けてくれたFUNさんに感謝なのはモチロン、参加されたメンバーの試行錯誤が互いのスキルupに繋がる様に・・・またザブザブしましょうね~
真冬の海での再乗艇訓練、ホントにお疲れ様でした! m(_ _)m
タグ :カヤックフィッシング再乗艇
2010年08月04日
カヤック再乗艇のススメ。
保管場所・車載・購入資金などなど・・・
幾つかの問題を克服すれば始める事の出来るカヤックフィッシング。
人気急上昇なこの釣りですが、大自然相手に予想外のアクシデントもあります!
釣師は釣果を求めてカヤックに乗る訳ですが、漕ぎ出す前には風や波の予報をチェック
(先の気象変化の予想)しています。
現場では刻々と変化する状況に応じて素早い行動を取らなければなりませんし、どんなに天候予測や安全に心がけていても・・・天候の急変をはじめ、万が一の可能性がある訳です。
そのうちの1つが・・・沈。 いわゆる、カヤックから海中へ落ちてしまうという事態です。
一般的には出艇や着岸時の比率が多いんですが、沖でもウネリがぶつかり合って発生する三角波やボトム変化で急にホレてしまうウネリ、動力船の通過による波、アングラーのミスによるルアーの根掛かりやアンカーを引っ張ってバランス崩したり・・・etc。
ほんの1例ですが、常に沈と隣り合わせの釣りがカヤックフィッシングです。
で、万が一カヤックから沈した時は再乗艇すればイイだけの話なんですが、
知識や経験無くして果たして可能なのか?
という訳で、再乗艇は必須科目として必ず練習しとくべきだと考えます。
まだチャレンジしていない方こそ、水温の高い今の時期に足の届く凪ぎの海から初めるのが難易度低くてオススメです。
慣れてきたならば徐々に荒海に挑戦し、必ず再乗艇が出来るという自信を持ってから沖に出る様にしたいですね~。
沈と言ってもカヤックの状態には2種類あって・・・再乗艇の難易度もUPします!
カヤックは正常で浮いてる場合・・・そのまま這い上がればOK。
カヤックが裏返り浮いてる場合・・・元にひっくり返してから這い上がればOK。
▼それでは、カヤックの状態別に再乗艇をしてみます。

いきなり沖は危険なので、まずは足の届く場所で練習して下さい。
今回は艤装や荷物は全て取り外しています。
慣れてきたら徐々に実釣時の装備での練習が理想的と思います。
▼まずは普段着ているPFD(フローティングベスト)で実際に浮かんでみましょう!

個人の体格差やPFDの装着ポジションで浮かぶ状態にも差があります。
「どれ位浮かぶのか」とか、「身動きの不自由さ」などを体感しておく事が大切。
経験していれば安心感がUPし落ち着いて行動する事が可能になるでしょう!
沈を想定しての訓練ですので、自分とカヤックを結ぶリーシュコード等は繋いでおきます。
風でカヤックが流されてしまっては、どんなに泳いでも追いつけない場合があります。
▼ 『ケース① カヤックは正常の状態での再乗艇』

カヤックの上に這い上がる為には、トグルなどを掴んで体をカヤックの上に運ぶ訳ですが・・・
この時、片手で自分側のトグルを掴み、もう片手は反対側のトグル目指して伸ばします。
で、バタ足して一気に反対側のトグルが掴めれば問題ありません。
無理な場合は自分側のトグル付近に体重を乗せれば、簡単に反対側のトグルが自分の
方に持ち上がって来ます。 この瞬間にすかさずガシッと握りましょう!
▼呼吸を整え、一気にカヤック上へ這い上がります。

腕の力で上体をカヤックの上に引き上げ、同時にバタ足して勢いをプラスします。
ポイントは、上体を引きずり上げるのではなくカヤックを体の下に引き込むイメージ!
足もずっとバタバタするのではなく、2~3度力強く蹴って瞬間的に推進力を得る事です。
スタンスは足を閉じているよりも、多少開き気味の方がバランス取り易いです。
ここまでの一連の動作を連続技として行える様になれば・・・
トグルを掴む為にカヤックを自分側に引き起こし、カヤックが倒れる反動を利用して
一気に這い上がる事も可能となりますので頑張って練習してみましょう!
▼上体がカヤックに乗ったら、バランスを取りながら体を捻って座ります。

▼最後に足を乗せてシートに座ればOKです。

続いては・・・
▼ 『ケース② カヤックが裏返った状態での再乗艇』

カヤックが裏返った状態にする為に、あえてグルッとダイブしてみます。
わざわざダイブする理由ですが・・・
カヤックから落ちる感覚や落水してから体が浮かび上がるまでの状況を把握する為!
ついでにカヤックがひっくり返る限界値を体に覚えさせたりと。
▼実釣では波や流れに強いライドですが、凪ぎの水面でも体重移動だけで・・・

簡単にひっくり返ります。
落水した瞬間にPFDの浮力に体が支えられ、体の上からカヤックが滑り落ちる感じでした。
あまりにも浅いとボトムに激突してしまう可能性があるので注意して下さい。
ちなみに、この時のボトムは砂で足が届かない水深です。
▼必ずカヤックの横へ脱出して下さい。

PFDを着ていても、落ちた勢い次第では頭が一瞬海中に潜ります。
浮かび上がった体上にカヤックがあると呼吸が出来ません!
その状態から再度潜ってカヤックの横に顔を出すには、PFDの浮力が邪魔になって苦戦
する可能性も。 海中で目を開けて、しっかりとカヤックの位置を把握しましょう。
カヤックがひっくり返ったら、基本的には裏返ったカヤックのボトムを這い上がって反対側のトグルを掴んだり、スカッパーホール・溝・キールなどの指の引っ掛かる部分を利用して上手くカヤックを裏返す事になります。
また、先程と同様に自分側のトグル付近に体重を乗せれば反対側が持ち上がってきますが、裏返ったカヤックのボトムを這い上がる方がライドの場合は難易度が高いので・・・
ここでのっちが考案したカヤッくるんの出番になります!
▼スカッパーホールに挿入して・・・ ▼ギュッと握って後ろに体重移動~


▼自分側のトグルを真下に押すイメージで一気にひっくり返します。

後は先程と同じ様にカヤックに再乗艇するだけ。
今まで触れてませんでしたが、リーシュコードについての問題と対処法が・・・
各々、リーシュコードを繋いでる場所は様々かと思います。
どんな場所に繋いでいたとしても、カヤックが裏返って落水し、後にカヤックを自分の方へ
回転させて裏返せばリーシュコードがカヤックを1周します。
で、再乗艇する訳ですから最低でもリーシュコードはカヤック1周分+αの長さが必要かと。
もしくは、コイル状や伸縮性のあるゴム製の製品を選ぶのが無難だと思います。
また、カヤック伝いにグルッと回る方法もありますが、リーシュコードを繋いだままだとそれ
なりの長さは必要です。
一時的にリーシュコードを外して付け直すのもアリですが、もしも荒れた海で失敗したら・・・
のっちは「BB用の手首タイプ・コイル状」にデカいカラビナ装着して使用しています。
▼各セクションごとに一呼吸入れてののっちの再乗艇訓練、ダイジェストでご覧下さい。
今回の記事用の写真や動画を撮影するのに、数え切れない程ダイブして再乗艇しました。
楽しいし暑い時期は気持ちイイので、海水浴がてらに是非チャレンジしてみて下さい。
▼一方、たむぞうさんはリーシュコードに問題アリでちょっと苦戦。
リーシュコードに伸縮性が無く短い事もあって、乗り込み時に突っ張るし座るのに体の自由が規制されてしまいます。
お陰で良い教訓となりました。体を張ってのチャレンジに感謝します。
▼グルグル回り過ぎてヘトヘトですが・・・ ▼ゴムハッチのライドは全く浸水してません!


各カヤックごとにハッチの構造が違うので・・・
噂では大量に浸水するタイプのカヤックもあると聞いた事があります。
例えば、裏返ったカヤックをひっく返す時にハッチから勢い良く浸水してしまって、
再乗艇してもバランス取れずにそのままひっくり返るとか・・・。
ビルジポンプで排出してからでないと再乗艇は不可能らしいです。
自分の艇がどれ位浸水するのかを把握する為にも、グルグル回転にチャレンジしましょう。
以上、「再乗艇のススメ」という事で書いてみましたが・・・
これは「再乗艇の方法をマスターする為の訓練」です!
凪ぎの海で装備無しならば簡単に出来る再乗艇。
ですが、なかなか荒海で練習したという話は聞きません。
本来なら荒海での訓練が必須なのでしょうが、いきなりでは危険が多すぎかと。
なので、まずは「方法をマスター」するのが先決と考えます。
で、マスターしたならば徐々にハードル上げて怪我しない程度にチャレンジです。。。
幾つかの問題を克服すれば始める事の出来るカヤックフィッシング。
人気急上昇なこの釣りですが、大自然相手に予想外のアクシデントもあります!
釣師は釣果を求めてカヤックに乗る訳ですが、漕ぎ出す前には風や波の予報をチェック
(先の気象変化の予想)しています。
現場では刻々と変化する状況に応じて素早い行動を取らなければなりませんし、どんなに天候予測や安全に心がけていても・・・天候の急変をはじめ、万が一の可能性がある訳です。
そのうちの1つが・・・沈。 いわゆる、カヤックから海中へ落ちてしまうという事態です。
一般的には出艇や着岸時の比率が多いんですが、沖でもウネリがぶつかり合って発生する三角波やボトム変化で急にホレてしまうウネリ、動力船の通過による波、アングラーのミスによるルアーの根掛かりやアンカーを引っ張ってバランス崩したり・・・etc。
ほんの1例ですが、常に沈と隣り合わせの釣りがカヤックフィッシングです。
で、万が一カヤックから沈した時は再乗艇すればイイだけの話なんですが、
知識や経験無くして果たして可能なのか?
という訳で、再乗艇は必須科目として必ず練習しとくべきだと考えます。
まだチャレンジしていない方こそ、水温の高い今の時期に足の届く凪ぎの海から初めるのが難易度低くてオススメです。
慣れてきたならば徐々に荒海に挑戦し、必ず再乗艇が出来るという自信を持ってから沖に出る様にしたいですね~。
沈と言ってもカヤックの状態には2種類あって・・・再乗艇の難易度もUPします!
カヤックは正常で浮いてる場合・・・そのまま這い上がればOK。
カヤックが裏返り浮いてる場合・・・元にひっくり返してから這い上がればOK。
▼それでは、カヤックの状態別に再乗艇をしてみます。

いきなり沖は危険なので、まずは足の届く場所で練習して下さい。
今回は艤装や荷物は全て取り外しています。
慣れてきたら徐々に実釣時の装備での練習が理想的と思います。
▼まずは普段着ているPFD(フローティングベスト)で実際に浮かんでみましょう!

個人の体格差やPFDの装着ポジションで浮かぶ状態にも差があります。
「どれ位浮かぶのか」とか、「身動きの不自由さ」などを体感しておく事が大切。
経験していれば安心感がUPし落ち着いて行動する事が可能になるでしょう!
沈を想定しての訓練ですので、自分とカヤックを結ぶリーシュコード等は繋いでおきます。
風でカヤックが流されてしまっては、どんなに泳いでも追いつけない場合があります。
▼ 『ケース① カヤックは正常の状態での再乗艇』

カヤックの上に這い上がる為には、トグルなどを掴んで体をカヤックの上に運ぶ訳ですが・・・
この時、片手で自分側のトグルを掴み、もう片手は反対側のトグル目指して伸ばします。
で、バタ足して一気に反対側のトグルが掴めれば問題ありません。
無理な場合は自分側のトグル付近に体重を乗せれば、簡単に反対側のトグルが自分の
方に持ち上がって来ます。 この瞬間にすかさずガシッと握りましょう!
▼呼吸を整え、一気にカヤック上へ這い上がります。

腕の力で上体をカヤックの上に引き上げ、同時にバタ足して勢いをプラスします。
ポイントは、上体を引きずり上げるのではなくカヤックを体の下に引き込むイメージ!
足もずっとバタバタするのではなく、2~3度力強く蹴って瞬間的に推進力を得る事です。
スタンスは足を閉じているよりも、多少開き気味の方がバランス取り易いです。
ここまでの一連の動作を連続技として行える様になれば・・・
トグルを掴む為にカヤックを自分側に引き起こし、カヤックが倒れる反動を利用して
一気に這い上がる事も可能となりますので頑張って練習してみましょう!
▼上体がカヤックに乗ったら、バランスを取りながら体を捻って座ります。

▼最後に足を乗せてシートに座ればOKです。

続いては・・・
▼ 『ケース② カヤックが裏返った状態での再乗艇』

カヤックが裏返った状態にする為に、あえてグルッとダイブしてみます。
わざわざダイブする理由ですが・・・
カヤックから落ちる感覚や落水してから体が浮かび上がるまでの状況を把握する為!
ついでにカヤックがひっくり返る限界値を体に覚えさせたりと。
▼実釣では波や流れに強いライドですが、凪ぎの水面でも体重移動だけで・・・

簡単にひっくり返ります。
落水した瞬間にPFDの浮力に体が支えられ、体の上からカヤックが滑り落ちる感じでした。
あまりにも浅いとボトムに激突してしまう可能性があるので注意して下さい。
ちなみに、この時のボトムは砂で足が届かない水深です。
▼必ずカヤックの横へ脱出して下さい。

PFDを着ていても、落ちた勢い次第では頭が一瞬海中に潜ります。
浮かび上がった体上にカヤックがあると呼吸が出来ません!
その状態から再度潜ってカヤックの横に顔を出すには、PFDの浮力が邪魔になって苦戦
する可能性も。 海中で目を開けて、しっかりとカヤックの位置を把握しましょう。
カヤックがひっくり返ったら、基本的には裏返ったカヤックのボトムを這い上がって反対側のトグルを掴んだり、スカッパーホール・溝・キールなどの指の引っ掛かる部分を利用して上手くカヤックを裏返す事になります。
また、先程と同様に自分側のトグル付近に体重を乗せれば反対側が持ち上がってきますが、裏返ったカヤックのボトムを這い上がる方がライドの場合は難易度が高いので・・・
ここでのっちが考案したカヤッくるんの出番になります!
▼スカッパーホールに挿入して・・・ ▼ギュッと握って後ろに体重移動~


▼自分側のトグルを真下に押すイメージで一気にひっくり返します。

後は先程と同じ様にカヤックに再乗艇するだけ。
今まで触れてませんでしたが、リーシュコードについての問題と対処法が・・・
各々、リーシュコードを繋いでる場所は様々かと思います。
どんな場所に繋いでいたとしても、カヤックが裏返って落水し、後にカヤックを自分の方へ
回転させて裏返せばリーシュコードがカヤックを1周します。
で、再乗艇する訳ですから最低でもリーシュコードはカヤック1周分+αの長さが必要かと。
もしくは、コイル状や伸縮性のあるゴム製の製品を選ぶのが無難だと思います。
また、カヤック伝いにグルッと回る方法もありますが、リーシュコードを繋いだままだとそれ
なりの長さは必要です。
一時的にリーシュコードを外して付け直すのもアリですが、もしも荒れた海で失敗したら・・・
のっちは「BB用の手首タイプ・コイル状」にデカいカラビナ装着して使用しています。
▼各セクションごとに一呼吸入れてののっちの再乗艇訓練、ダイジェストでご覧下さい。
今回の記事用の写真や動画を撮影するのに、数え切れない程ダイブして再乗艇しました。
楽しいし暑い時期は気持ちイイので、海水浴がてらに是非チャレンジしてみて下さい。
▼一方、たむぞうさんはリーシュコードに問題アリでちょっと苦戦。
リーシュコードに伸縮性が無く短い事もあって、乗り込み時に突っ張るし座るのに体の自由が規制されてしまいます。
お陰で良い教訓となりました。体を張ってのチャレンジに感謝します。
▼グルグル回り過ぎてヘトヘトですが・・・ ▼ゴムハッチのライドは全く浸水してません!


各カヤックごとにハッチの構造が違うので・・・
噂では大量に浸水するタイプのカヤックもあると聞いた事があります。
例えば、裏返ったカヤックをひっく返す時にハッチから勢い良く浸水してしまって、
再乗艇してもバランス取れずにそのままひっくり返るとか・・・。
ビルジポンプで排出してからでないと再乗艇は不可能らしいです。
自分の艇がどれ位浸水するのかを把握する為にも、グルグル回転にチャレンジしましょう。
以上、「再乗艇のススメ」という事で書いてみましたが・・・
これは「再乗艇の方法をマスターする為の訓練」です!
凪ぎの海で装備無しならば簡単に出来る再乗艇。
ですが、なかなか荒海で練習したという話は聞きません。
本来なら荒海での訓練が必須なのでしょうが、いきなりでは危険が多すぎかと。
なので、まずは「方法をマスター」するのが先決と考えます。
で、マスターしたならば徐々にハードル上げて怪我しない程度にチャレンジです。。。
2010年07月24日
再乗艇のお助けアイテム
万が一の沈に備えて、カヤック再乗艇の練習をしようと考えてたのっち。
もしも沈してカヤックがひっくり返ったら、基本的には裏返ったカヤックのボトムを這い上がって反対側のトグル(ハンドル)を掴んだり、スカッパーホール・溝・キールなどの指の引っ掛かる部分を利用して上手く裏返す(元に戻す)事になります。
ただ、ライドの様な幅広でボトムが面ツルだと、荒れた海でトグルが掴めなかった場合にカヤック元に戻すのに苦戦しそう。 (汗)
しかも冬場はウェーダースタイルなので、浸水した場合カヤックに這い上がってトグルを掴むのは困難かと・・・。
それが心配で、以前からこんなアイテムを作って常備していました。
(先日、実際に使用してみて便利だったので、ようやく記事にする事となりました。)
▼『登録商標』 カヤッくるん (嘘)

作るのに準備した物は・・・
・犬の散歩用のリード (我が家の茶々丸が齧って切れてしまった物)
・ランディングネットをショート加工した時にカットしたアルミパイプ
・そこら辺に転がってたナットとワッシャー (ステンレス)
全て廃材の再利用です。 ♪
作り方は簡単で、パイプにドリルでリードが通せるサイズの穴を開けて・・・
▼穴に通したリードに、こんな感じでワッシャーとナットを挟んで結び目を入れるだけ。

▼後はリードの輪っかを引っ張ればワッシャー部で止まります!

このステンナットのお陰で、パイプの片側に重心が片寄ります。 (ココがポイント!)
▼たまたまPFDのプライヤーホルダーにピッタリでした。

「カヤッくるん」の使い方ですが・・・
▼裏返ったカヤックのセンター付近のスカッパーホール(自分から遠い方)に差し込みます。

(パイプからリードの端が出てますが、この時点では長さの調整確認したかったので、
実際は端が出て無い物とお考え下さい。)
ポイントは、ナットが入ってる側(重心の重い側)から穴に挿入する事!
そうすれば、ナットの重みで自然に海中へとパイプ部全てがスカッパーホールを通過します。
▼で、輪の部分をしっかり握って引っ張ると・・・

この時、自分側のトグルを下方向(海底)に押しながらグッと輪っかを引っ張ると簡単にカヤックはひっくり返りました。 ♪
▼コックピット側にはこんな感じでフッキングしています。

後は落ち着いて再乗艇を済ませてから「カヤッくるん」を引き抜くだけです。
普通にトグルを掴んでひっくり返せるのならば問題ありませんが、自信のない方や体格の小柄な方などには便利なアイテムになるかと思います。
(のっちの場合はコレ使わなくても普通のスタイルで簡単にでひっくり返せましたが。)
自作する場合ですが、各カヤックによってスカッパーホールの場所が様々ですので、パイプの長さやリードの長さは各々微調整して下さい。
もしかしたら、実際にこんなアイテムがカヤック別に商品化されちゃったりして。。。 (笑)
もしも沈してカヤックがひっくり返ったら、基本的には裏返ったカヤックのボトムを這い上がって反対側のトグル(ハンドル)を掴んだり、スカッパーホール・溝・キールなどの指の引っ掛かる部分を利用して上手く裏返す(元に戻す)事になります。
ただ、ライドの様な幅広でボトムが面ツルだと、荒れた海でトグルが掴めなかった場合にカヤック元に戻すのに苦戦しそう。 (汗)
しかも冬場はウェーダースタイルなので、浸水した場合カヤックに這い上がってトグルを掴むのは困難かと・・・。
それが心配で、以前からこんなアイテムを作って常備していました。
(先日、実際に使用してみて便利だったので、ようやく記事にする事となりました。)
▼『登録商標』 カヤッくるん (嘘)

作るのに準備した物は・・・
・犬の散歩用のリード (我が家の茶々丸が齧って切れてしまった物)
・ランディングネットをショート加工した時にカットしたアルミパイプ
・そこら辺に転がってたナットとワッシャー (ステンレス)
全て廃材の再利用です。 ♪
作り方は簡単で、パイプにドリルでリードが通せるサイズの穴を開けて・・・
▼穴に通したリードに、こんな感じでワッシャーとナットを挟んで結び目を入れるだけ。

▼後はリードの輪っかを引っ張ればワッシャー部で止まります!

このステンナットのお陰で、パイプの片側に重心が片寄ります。 (ココがポイント!)
▼たまたまPFDのプライヤーホルダーにピッタリでした。

「カヤッくるん」の使い方ですが・・・
▼裏返ったカヤックのセンター付近のスカッパーホール(自分から遠い方)に差し込みます。

(パイプからリードの端が出てますが、この時点では長さの調整確認したかったので、
実際は端が出て無い物とお考え下さい。)
ポイントは、ナットが入ってる側(重心の重い側)から穴に挿入する事!
そうすれば、ナットの重みで自然に海中へとパイプ部全てがスカッパーホールを通過します。
▼で、輪の部分をしっかり握って引っ張ると・・・

この時、自分側のトグルを下方向(海底)に押しながらグッと輪っかを引っ張ると簡単にカヤックはひっくり返りました。 ♪
▼コックピット側にはこんな感じでフッキングしています。

後は落ち着いて再乗艇を済ませてから「カヤッくるん」を引き抜くだけです。
普通にトグルを掴んでひっくり返せるのならば問題ありませんが、自信のない方や体格の小柄な方などには便利なアイテムになるかと思います。
(のっちの場合はコレ使わなくても普通のスタイルで簡単にでひっくり返せましたが。)
自作する場合ですが、各カヤックによってスカッパーホールの場所が様々ですので、パイプの長さやリードの長さは各々微調整して下さい。
もしかしたら、実際にこんなアイテムがカヤック別に商品化されちゃったりして。。。 (笑)
タグ :カヤックフィッシング再乗艇